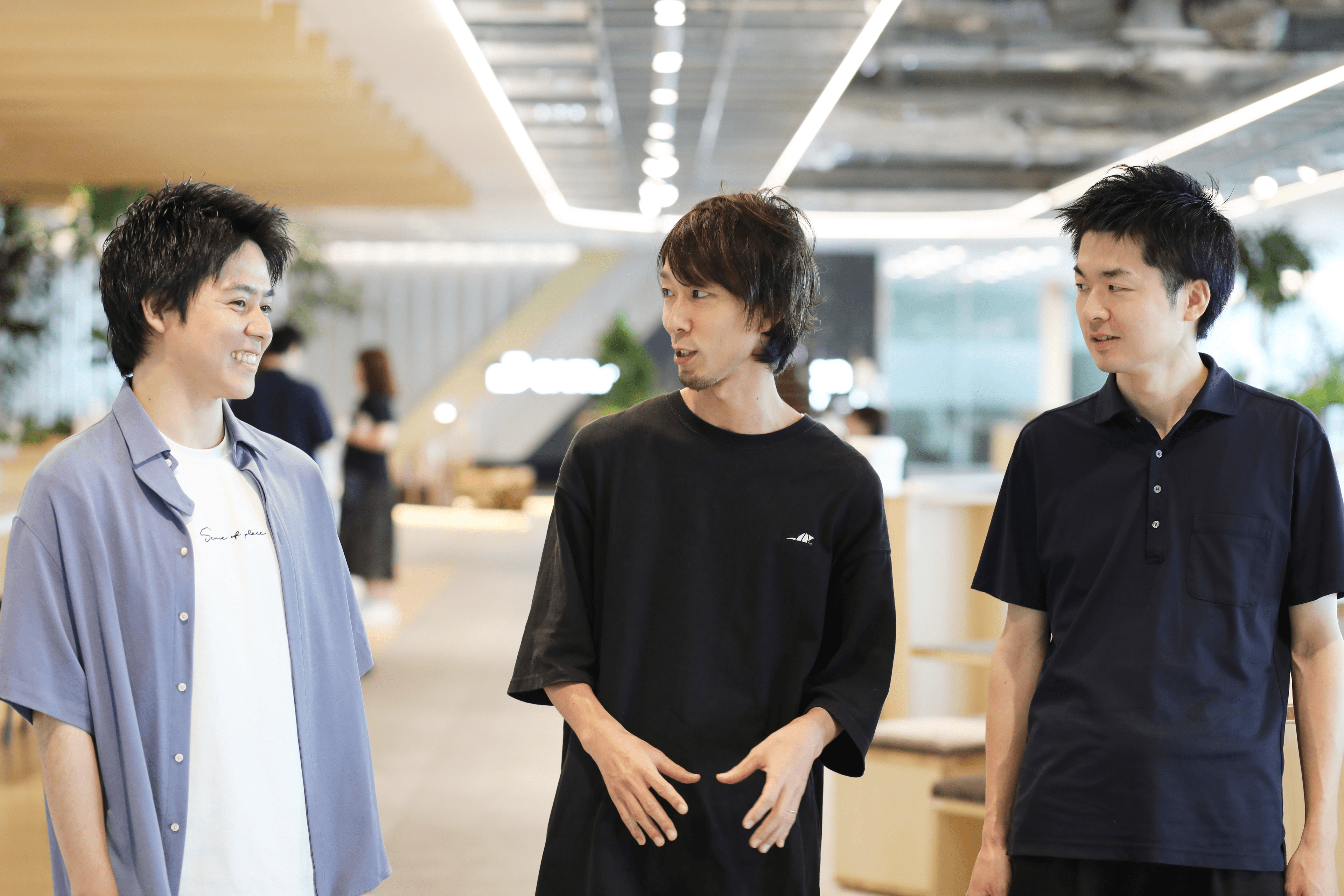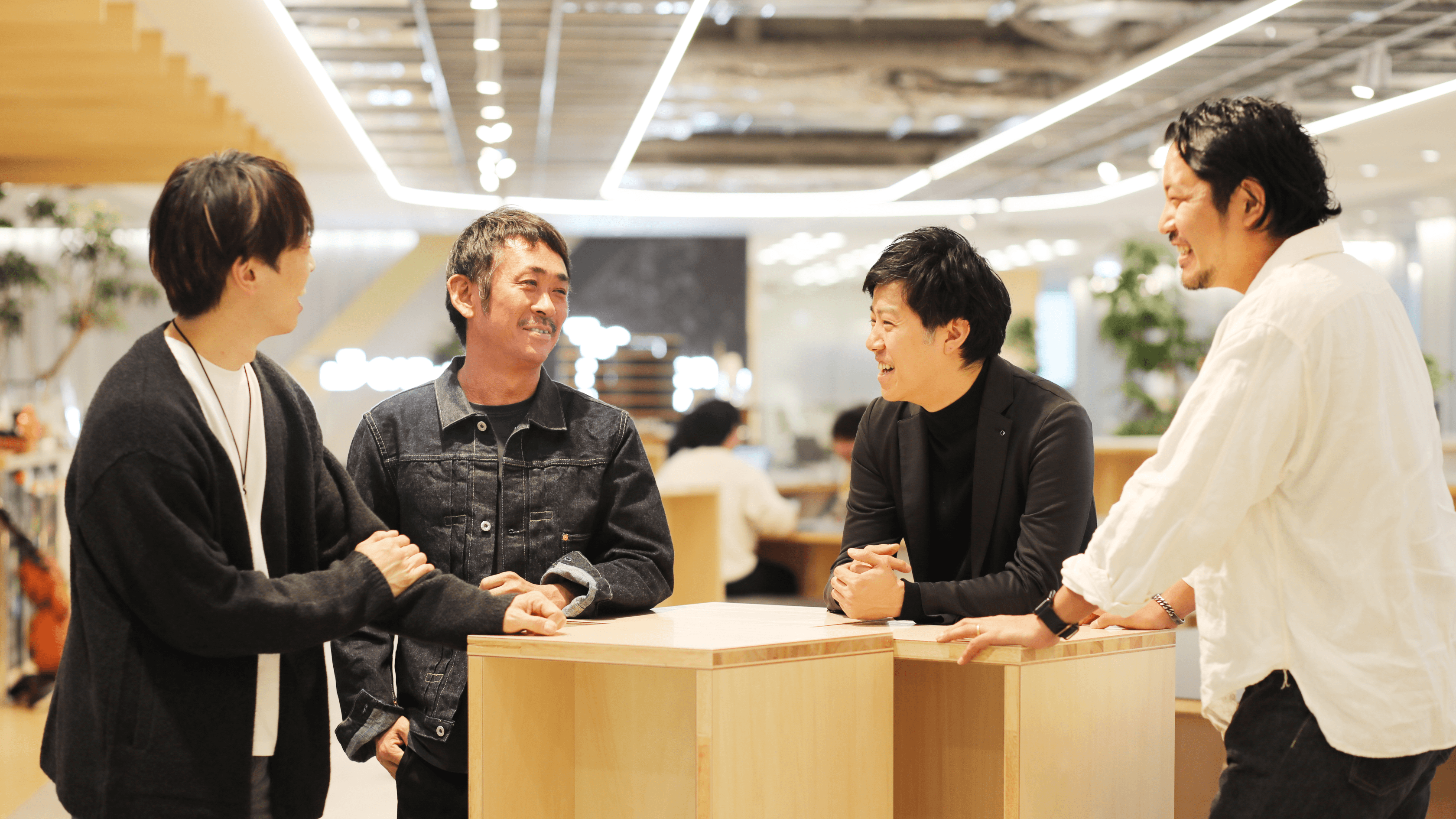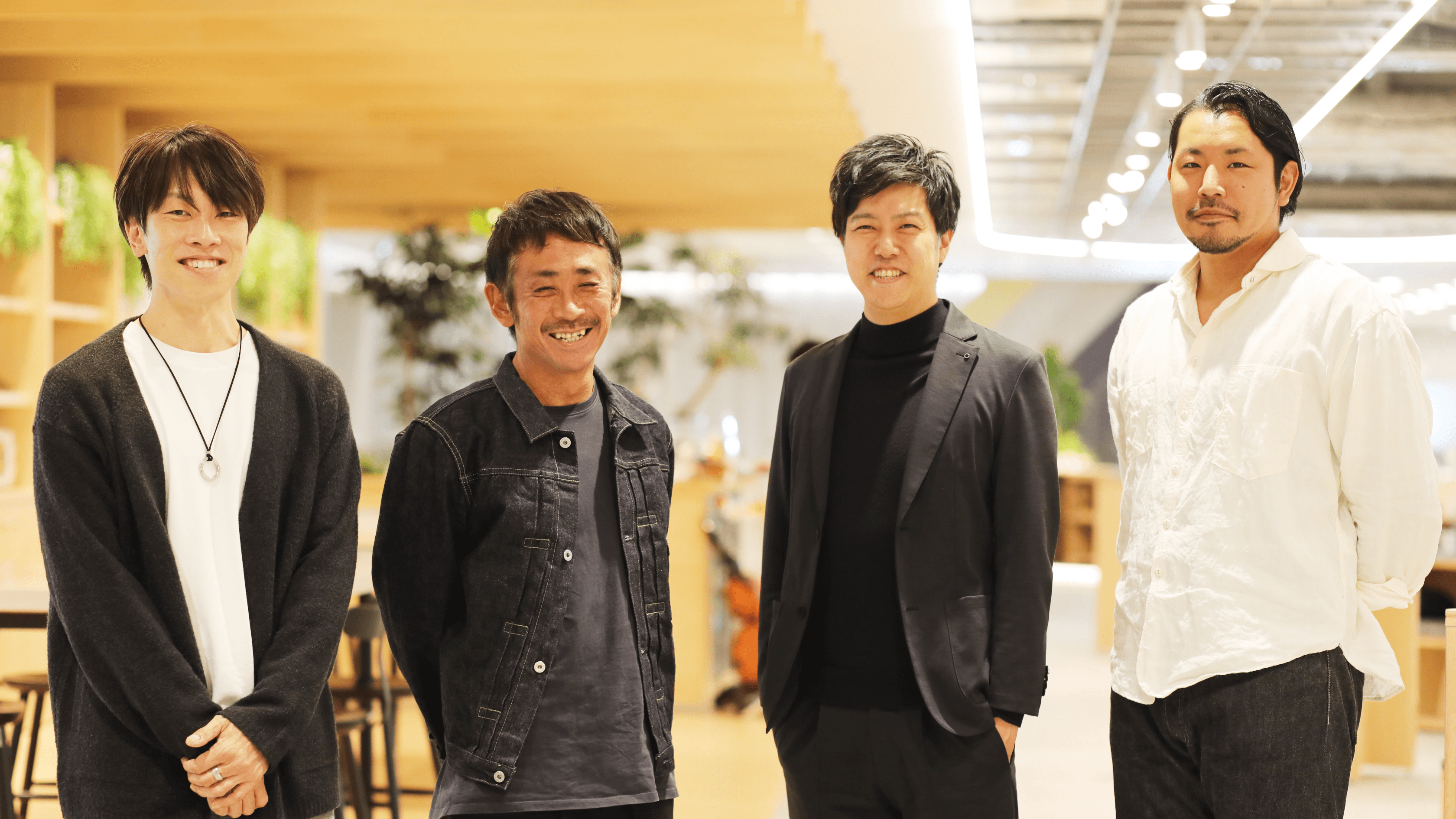採用情報

事業成長を支える広告運用。CARTA ZEROで磨く市場価値の高いプロフェッショナル
Interview Member
自分の知見を活かす、広告運用の視野を広げるキャリア選択
Q_前職での仕事内容と、転職を考えたきっかけを教えてください。
中村: 前職ではアプリ広告中心の代理店でゲームアプリの広告運用を行っていました。戦略立案、シミュレーション作成、入稿、運用効果の改善提案など幅広く担当していました。転職を考えたきっかけは、運用スキルをより成長させたいと考えたためです。市場ではアプリ広告よりもWEB広告に需要があり、規模も大きいです。また、前職ではアプリ広告における主要媒体が一部に限られていたため、より多くの媒体を扱いたいと考えていました。これまでの知見を活かせるアプリ広告とWEB広告の両方に携わることができる環境で活躍したいと、CARTA ZEROへの転職を決めました。
石渡: 私は前職で広告制作会社の営業をしておりました。商材はイラストや動画、WEBサイトなど多岐にわたり、ディレクション業務を兼務することもありました。転職を考えた理由は、クリエイティブの知見を広告運用という形で活かし、企業の事業成長をより本質的なレベルで実現したいと思ったことです。前職では制作関連の業務が中心でしたが、その中で企業のマーケティング活動がデジタルにシフトしていくのを感じていました。また、制作物の「その先」、つまり運用によって成果を出すことの重要性も感じていました。クリエイティブの知見を活かしながら運用まで手掛けることで、自身のスキルアップにも繋がりますし、クライアントにもより質の高い貢献ができると考えたのがきっかけでした。
Q_数ある広告代理店やマーケティング企業の中で、CARTA ZEROへの入社の「決め手」は何でしたか?
中村: 主に2つあります。1つは幅広い事業領域がある環境で、多様な知見を持った社員と働けることです。CARTA ZEROは海外企業の案件取り扱いもありグローバルに活躍するメンバーが多いので、これまでにない刺激を受けられます。言語の壁や運用方法の違いなど大変な部分もありますが、知見の幅が広がる環境です。もう1つは、面接で出会ったすべての社員が魅力的だったからです。面接を通して、気持ちよくコミュニケーションしながら仕事ができる環境が容易に想像できました。自分のスキルをCARTA ZEROでどう活かせるのか懸命にすり合わせていただく場面も随所に見られ、ここでなら「これまでのスキルを発揮し、貢献できる」と感じられました。
Q_石渡さんは制作会社の営業をしていたとのことで、「広告運用コンサルタント」に未経験から挑戦する上で不安はありましたか?
石渡: はい。当初は、自分が広告運用のプロとして皆さんと一緒に活躍できるのか、不安も正直ありました。ただ当時OJT担当だった丹羽が、右も左も分からなかった私に、丁寧に教えてくれましたし、チームの皆さんもしっかりとサポートしてくれました。
未経験でも一歩踏み出せる環境だと感じられたのは、会社のバリューのひとつ『挑戦しよう。』という文化が、一人ひとりに浸透していることも大きいです。大型クライアントや未経験の業種の案件等に挑戦したいと手を挙げた際も、チームメンバーが快く歓迎してくれました!運用の幅に限界を感じ、より大きな案件に挑戦したいと思ったタイミングで周囲がサポートしてくれたことは心強かったです。
Q_実際には、どのようなOJTを行っているのですか?
丹羽: 私は何かを教えるとき、あえて業務の1から10まですべてを伝えることはしません。最初に全体像を見せてしまうと、その枠にとらわれて自由な発想がしにくくなるからです。意識しているのは、「1~3」だけを教えること。そこから先の「10」や「15」には、自分で考えてたどり着けるようなヒントや考え方を渡すようにしています。実際に考えてもらったうえでアイデアを聞き、私の案も伝えて、出てきた案をまずは試してみる。このプロセスを繰り返すことで、自然と“自分で考える力”が身についていくと考えています。
Q_入社してみて、良いギャップや、逆に「大変だった」ことはありますか?
中村: 選考過程で出会った社員に加え、一緒に働く社員も親しみやすいことが良いギャップでした。コミュニケーションコストがかからず、スムーズに仕事ができますし、精神的にも気持ちよく働くことができています。立場にこだわらず、まずは提案をしっかりと聞いてくれる仲間が多いため、考えを素直にアウトプットできる環境です。一方で、自社アドネットワークの運用は思った以上に大変でした。大手の媒体に比べ、自社のZucks媒体は数多くのメディアに対しての単価調整があり、想像以上に対応する事が多くあります。しかし、おかげでメディアの知見に対する見方は高まってきました。
石渡: 私も役職に関わらず、フラットにコミュニケーションが取れることが良いギャップでした。上司や経営層にも気軽に相談できますし、会議でも自分の意見を伝えられます。中村も述べている通り、まず意見を受け入れてくれる雰囲気があるので、過度にかしこまらず本音で話すことができますね。大変だったことは、自分が未経験だったということもあり、CPCやCPIなど専門用語が多かったことです。会議の場でも内容を理解するのに精一杯だったことも多々ありました。

自社プロダクトならではの強みを活かし、提案の質を高める
Q_コンサルタントの思考プロセスにおいて、Zucksのような自社プロダクトを扱う運用と一般的な大手媒体の運用はどのような点が異なりますか?
丹羽: 自社プロダクトの場合、広告主の収益最大化とメディアの収益最大化の2つのミッションがある点が異なると考えています。この二つ、実は相反するミッションで、非常に難易度が高いです。広告主が、より低コストで広告を配信したいというニーズと、メディアがより高い単価で広告を売りたいというニーズをいかに適切にマッチングさせるかが、重要な課題です。どのメディアに、どのようなデザインの広告を、どのタイミングで、どの単価で配信するか日々考えています。このプロセスは難しさを伴いますが、その奥深さこそが広告運用の面白さでもあると感じています。
Q_ 「自分のアイデアがプロダクトの機能改善に繋がった」というご経験はありますか?
丹羽:組織としての改善ですが、デザイナーチームを立ち上げた経験です。 Zucksアドネットワーク(以下Zucks ADNW)という自社プロダクトには広告配信単価の最適ロジックがありますが、これは一定のコンバージョンや配信実績がないと機能しません。つまり、ある程度成果を上げていないメディアは土俵に上がれない仕組みになっています。しかし、私の経験からは、土台にあげた方がいいメディアが存在するため、それらをしっかり活用する運用を行うようにしました。変更当時は代理店経由での配信が中心で、他社と差別化しにくい状況でした。そんな中で直接クライアントとの取引が始まり、「自社でクリエイティブも担えた方が成果につながるのでは」という課題意識が生まれました。現場を一番理解している運用チームが指揮をとる形でデザイナーチームを立ち上げたことで、これまで配信先の土台に上がっていなかったメディアの収益化・クライアントの広告効果改善に寄与し、結果的にZucks ADNWの改善につながったと感じています。
Q_ 自社プロダクトを「育てる」ことで、得られるやりがいを教えてください。
石渡: 日々運用をしていく中で得た知見やクライアントからの要望を開発局にフィードバックし、プロダクトの機能が増えていくことによって、以前は対応できなかった手法で課題解決できた時に、やりがいを感じますね。ただ、クライアントの要望を言われたとおりに叶えることが必ずしも正しいとは限らないです。本質的な課題を見極めて議論し、最適なアプローチを考えながらプロダクトを育てていくという視点が提案の質を大きく左右すると考えています。
中村: 新規案件に取り組む中で、クリエイティブチームと連携して表現方法を検討し、配信先の設計まで含めて他チームと協力して進めていく業務にやりがいを感じています。日々の業務を通じて理解を深めながら、もっと自分の意見を出せる力をつけたいです。
丹羽: 代理店の方々からパフォーマンス以外の面でもZucks ADNWが選ばれていく瞬間に、大きな達成感を感じます。各代理店の方々が私たちを選んでくださる理由には、パフォーマンスの良さやレスポンスの速さ、柔軟な運用力など、トータルとしてのプロダクトの強みがあります。どんなに優れたプロダクトでも、運用コンサルが機能していなければ良い成果は生まれないため、私たち広告運用チーム自体が商品の原動力になっていると思います。運用チームが最適な運用体制を整えることが大前提であり、そこからプロダクトが成長していくと考えています。
Q_自社プロダクトの運用に携われる環境は、ご自身をどう成長させたと感じますか?
石渡: 課題の本質を見極めるための思考の解像度が高まったこと、そしてそれに応えるためのスキルの引き出しが増えたことですね。自社プロダクトは運用の自由度が高いため、クライアントの課題に対してなぜこの手法が最適なのかを考え、自分で配信設計を組み立てる必要があります。配信して終わりではなく、結果を分析して調整を繰り返す必要があるので、常に思考をアップデートし続ける力が養われます。また、市場の変化も速く、既存の運用手法が通用しなくなる場面も多いため、新しい運用手法を自ら探し挑戦することが求められます。こうした挑戦の積み重ねによって、運用手法の引き出しが増え、以前は実現できなかったアプローチが可能になったと感じています。
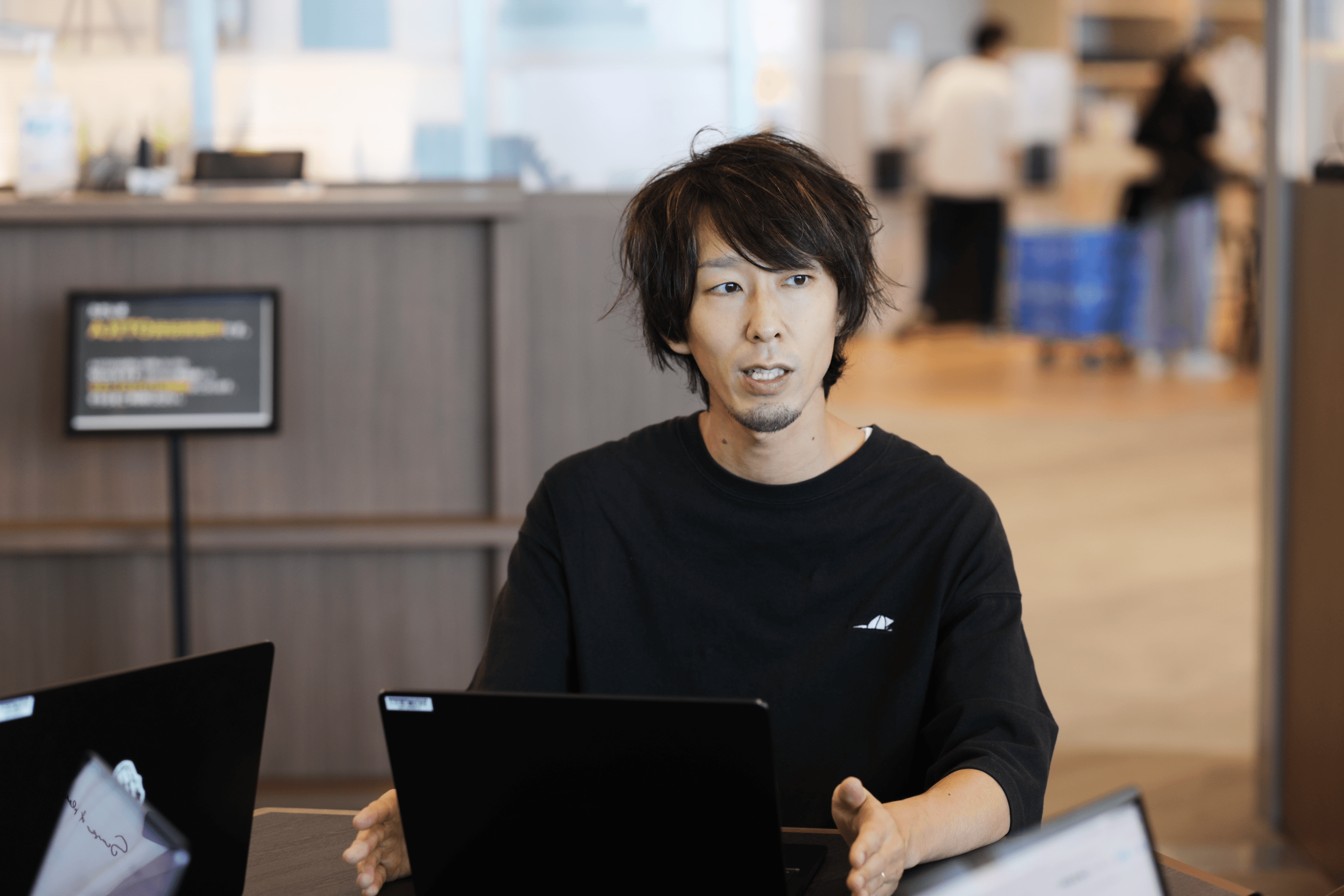
Q_最も印象に残っている案件について教えてください。
中村: 入社2か月後に担当した案件です。クライアント指定のクリエイティブのみで運用を行っていたのですが、獲得数が伸び悩んでいました。そこでセールス・デザイナーと話し合い、クライアントの意向も踏まえたうえで、当社オリジナルの広告フォーマットを用いたクリエイティブを作成しました。その結果、獲得だけでなくROASも大きく改善させ、先方からも一定の評価を頂くことができました。広告運用と聞くと管理画面に向き合うイメージを持つ方もいると思いますが、CARTA ZEROでは、より最適な成果を追いかけるための配信・クリエイティブ戦略含めた視点で経験を積めることができるため、運用を超えた強みを感じました。
石渡: 初めて経験した大型クライアントの案件です。予算の多い案件は、その分巻き込む社内のメンバーも多く、セールスはもちろん、クリエイティブやメディアリクルーティングチーム、アフィリエイトや外部媒体のコンサルメンバーなど大勢で話し合い、クリエイティブの制作から運用まで進めました。予算が多いため配信するクリエイティブやメディア数も膨大で、これまで以上にスピーディーかつ正確な調整が求められ、大きなプレッシャーを感じました。ただ、その経験は自信につながり、運用の幅が広がりましたね。
丹羽: 私は、入社してすぐに担当したマンガアプリの案件が印象的でした。ZucksADNWの中でも最古参の案件で、実質7年間にわたって運用を担当しました。私の退職後に売上が大きく落ち込んだこともあり、再入社後は強い思い入れを持って再び担当。クリエイティブディレクションから見直しました。その結果、数か月で売上を大きく回復させることができました。この成功の背景には、案件への深い理解と、マンガアプリの内容を徹底的に分析した上での設計がありました。また、今後は担当者に依存しすぎないよう、ノウハウを言語化して共有・育成したことで、チーム全体の力を高めることにもつながりました。
Q_海外案件ならではの醍醐味、同時にその『難しさ』はどのような点にあると思いますか?
丹羽: 海外のクライアントは意思決定が非常に速いです。広告運用も海外の感覚で進めるため、早いと3日で判断されることも。しかし、広告の学習を完了させるためには、ある程度のボリュームを出す必要があるため、あまりに早い判断はもったいないと伝えています。ただ、なかなか伝わらないこともあるのが難しいところです。この課題を解決するために、クライアントと直接やり取りをしているセールスチーム向けに、広告運用の理解を深める勉強会を開催しています。その部分をしっかりと見ていただけるような交渉を意識してセールスを行っています。国ごとに文化や考え方の違いがあるため、それぞれの国に合わせた攻略法をセールスと話し合いながら進める部分は、海外案件だからこそ経験できる醍醐味だと感じています。
Q_単なる「広告運用スキル」だけではない、どのような「ビジネス視点」が身についたと感じますか?
中村: 広告運用の成果を「コンバージョン数」といった指標だけで捉えるのではなく、それがクライアントへ長期的利益をもたらしているか、LTVやROASを最大化するにはどうするべきか、などクライアントの将来の事業成長を見据えた運用力や提案力が身についてきたように感じます。
石渡: そうですね。特に海外の大手クライアントを担当する際、単に運用するだけでなく、海外クライアントの傾向を把握し、先回りしてアクションを取ったり、時には文化的・社会的な文脈を理解した上で最適なコミュニケーションを取るというグローバルな視点が身についたと感じます。
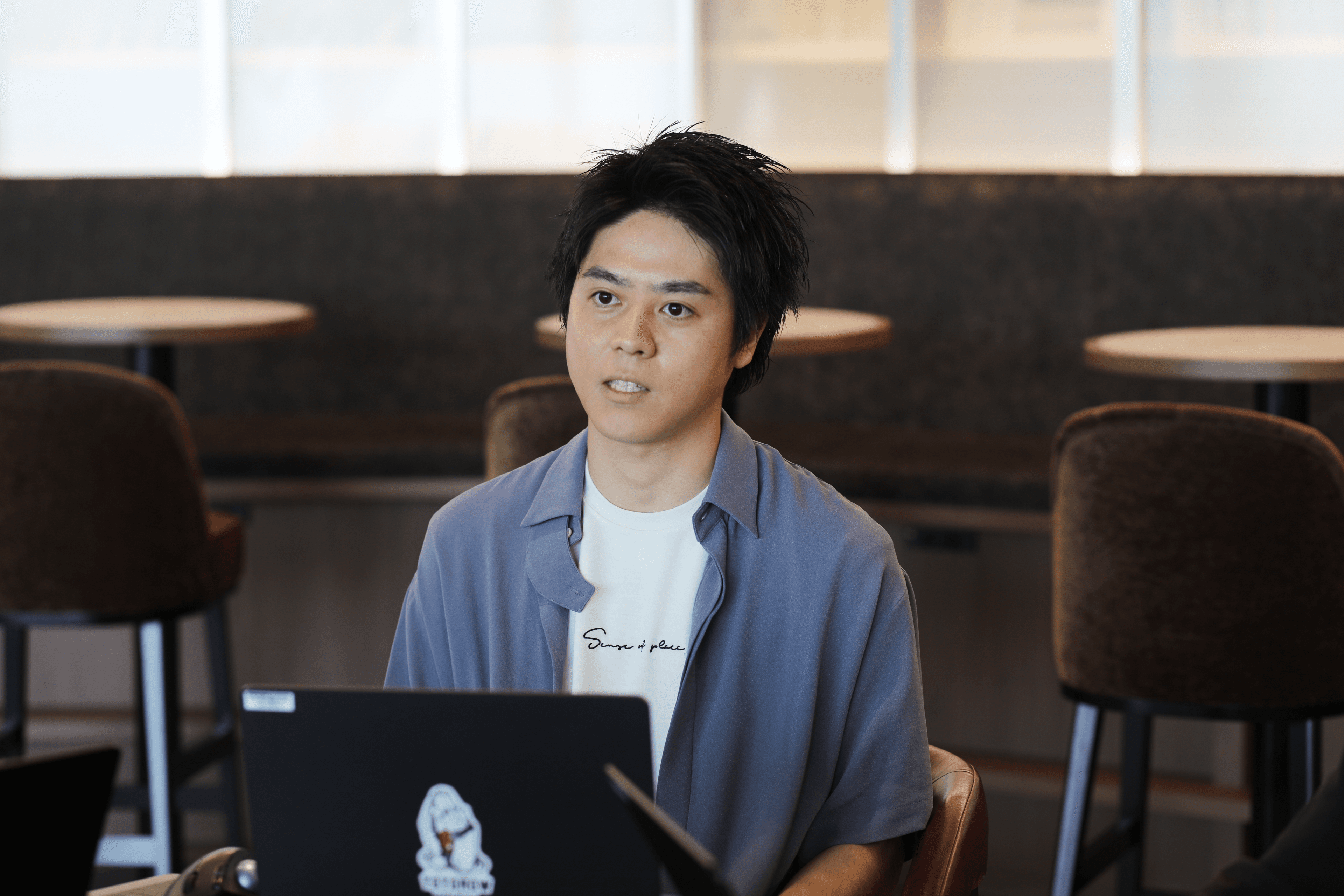
自社プロダクトを軸に広がるキャリアの可能性
Q_CARTA ZEROには「自ら問い、自ら動く姿勢」という文化がありますが、日々の業務で実感することはありますか?
中村: 例えば、メディア規制が変わり、現在のクリエイティブが使えなくなる可能性があるという情報をキャッチアップしたとき、即座に新しいクリエイティブを提案・作成したり、新たなメディアを見つけ出したりするメンバーがたくさんいます。そんな瞬間、「自ら問い、自ら動く姿勢」という文化を強く実感します。そもそもゲームアプリは流行り廃りが激しく、大人気だったゲームが1ヵ月後には人気がなくなることも珍しくありません。担当しているゲームの市場での立ち位置や、各メディアがどのような考えで弊社プロダクトを利用してくれているのかを常に意識し、俯瞰的に事象を捉えた上で、クリエイティブの作成や運用を行うよう心がけています。
石渡:私は、前例のない案件を担当する時に実感します。比較的ゲームジャンルの案件が多いですが、会社が大きくなるにつれて、ゲーム以外の案件を担当することも増えてきました。ゲームではビジネスモデルがある程度決まっているため、アプローチ方法も確立されています。一方で、それ以外の案件は業種やクライアントによってKPIが異なり、過去の事例が社内にないケースも多いです。誰も正解がわからない状況の中で、自分の知見を活かして確度の高い仮説を立て、適切なアプローチをすることが求められます。まさに「自ら問い、自ら動く姿勢」ですね。
Q_チームの雰囲気を一言で表すと?
丹羽:ロジカルな雰囲気のチームです。数字と向き合う仕事のため、感情よりも事実を重視して話す人が多く、その姿勢がチームの雰囲気にも影響しています。それぞれの情報の出どころを明確にすることを意識したコミュニケーションや情報交換が、自然に行われているチームだと感じます。もし情報が不明確な場合は、そのソースを明らかにする会話がよく生まれ、結果として全員で深堀しているような状態になります。
Q_チームで活躍するメンバーは、どのようなキャリアを歩んでいますか?CARTA ZEROならではの成長機会について教えてください。
丹羽: 広告プラットフォームのエンドポイントとなるチームのため、このチームでの経験は、社内のすべてのチームの業務につながります。どのチームに配属されても、最初はこの広告運用チームで研修を行うことが多いです。そのため、このチームで経験を積んだ後のキャリアパスは定まっていません。運用のプロフェッショナルを目指す道もあれば、プロダクトの成長に関心があればプロダクトマネージャーに進むこともあります。また、クライアント目線で成長に関わりたい場合はセールスにキャリアチェンジすることも可能です。決まったキャリアパスがないからこそ、自分たちで新しいキャリアを一緒に作り上げていけるのが、CARTA ZEROならではの特徴だと思います。
Q_入社してから、ご自身の市場価値はどのように高まったと感じますか?
中村: これまでは代理店での運用業務が中心だったため、主に「クライアントの売上」と「自社の売上」という2つの視点に重きを置いていました。しかし現在は自社アドネットワークの運用に携わっているため、見るべき視点が「クライアント」「メディア」「自社プロダクト」の3つに広がっています。提携しているメディアの収益にも目を向けながら運用を行う必要があると強く感じるようになりました。市場の変化に柔軟に対応しながら、自社プロダクトをどう拡張していくか、クライアントの売上をいかに最大化するかという点も常に意識しています。案件を拡大するだけでなく、プロダクト側の視点を持てるようになったことは、自分にとって大きな成長です。
石渡: 入社後は、営業から運用へのキャリアチェンジを行い、さまざまな国や商材の案件を担当する中で、自身の運用スキルを大きく高めることができたと感じています。その後、新しくリリースされた自社DSPプラットフォームの専属運用担当となり、ひとつのプラットフォームに専門分野を絞ったことで、他社の動向や市場トレンド、配信設計、プロダクト改善などに、より深く注力できるようになりました。また、自分の売上だけでなく、プロダクト単体の売上も担うようになったことで視座が高まり、1プレイヤーとしてだけでなく、会社全体の視点から物事を考えられるようになったことは、自分にとって大きな変化です。

チームで築く成長と新たな挑戦
Q_今後成し遂げたい夢や目標を教えてください。
中村: チームでは、自社プロダクトを多くのクライアントに選んでいただけるよう、運用面での実績を積みながら、プロダクトの精度向上に取り組んでいきたいです。個人では、Zucksの運用に加えて、前職で対応していた大手媒体の運用にも力を入れ、スキルをさらに磨きたいです。将来的にはチームメンバーの育成にも取り組んでいければと考えています。
石渡: まずは、昨年立ち上げたばかりの自社DSPプラットフォームを、自分だけでなく他のチームメンバーも運用できるように体制を整えていきたいです。運用できるメンバーが増え、対応できる案件数が拡大すれば、クライアントの事業成長にもより大きく貢献でき、会社全体の成長や事業規模の拡大にもつながると期待しています。
丹羽: CARTA ZEROとして新たなスタートを切ったことで、これまで実現できなかったことが少しずつ可能になっていくと感じています。統合した各社のリソースを最大限に活用し、これまでの既存の殻を破っていくことが、現在自分が成し遂げたい夢です。
Q_最後に、この記事を読んでいる未来の仲間へメッセージをお願いします。
丹羽: これまで広告運用を経験してきた方の中には、「もっとこうできたらいいのに」「自分が関われる範囲ってこれだけなのかな」など、もどかしさを感じたことがある方も多いと思います。Zucks ADNWは、そうした壁を打ち破るためのツールとして非常に適しています。新しいことに挑戦したい方や、広告運用の楽しさを改めて実感したい方と、ぜひ一緒に仕事がしたいです。「これまでにない広告運用に挑戦したい」という思いを持つ方とも、共にチャレンジしていけたら嬉しいです。